福岡大学で学び、挑戦し、夢を追う学生たちに迫るインタビュー企画、「ふくらませ、大胆に。」
学びに向き合う姿勢や将来への想い、日々のキャンパスライフを通した一人一人の個性と成長をお伝えします。
福岡大学経済学部の科目「ベンチャー起業論」で2025年度執行部を務める西田透眞さん(経済学部産業経済学科3年次生)は、“経営”が身近にある環境で育った。
宮崎県出身の彼が福大経済学部を進路先に選んだ理由は、「都会に出てみたいから」と「何にでもなれるような学部を選んでおこうと思ったから」だった。

そんな彼が1年次から「ベンチャー起業論」で学ぶことにしたのは、父親の影響が大きい。彼の父親は地元で建設会社を営む。彼は父親のことを、人気アニメの主人公『ルフィ』になぞらえる。中学校を卒業後、いろいろな職業を経験した後に創業した豪傑で、福岡や東京に営業所を持つまでに成長させたという。
そんな父親の背中を見て、「人をまとめるって大変そうだなと思っていました」と語る。一方で、同志や仲間を集め、グングン突き進んでいく経営者としての姿を「カッコいい」と思う気持ちもあった。
緩い選択の先にあった福大での学生生活で、「ベンチャー起業論」に出会う。「何か面白そうだな」と直感で受講することにした。
1年次に参加したチームでは、起業論に参画するコンサル企業が抱える、人事課題の解決に取り組んだ。テーマは『新卒採用のミスマッチ解消』。「人前で発言することが苦手で、積極性に欠ける性格」と自らを評する彼は、経験豊富な上級生や社会人を前に、ほとんど発言することができなかったという。
議論の内容を理解するのに精一杯で、ただ先輩に付いていくことしかできなかった。だが、社会人相手に堂々と議論を重ねる先輩たちの姿に触れ、「自分もああなりたい」「苦手なことを克服していきたい」と挑戦する意欲が芽生えた。
2年次には副リーダーとしてプロジェクト運営を任される。全体を見渡す立場になり、チームビルディングの難しさを痛感した。言葉の伝え方によって、相手との間に壁ができたと感じたこともある。
「一つ解決したと思えば、別の課題が出てくる。全体のバランスを取るのが本当に難しかった」。
2年次に参加したチームでは、空き家の賃貸活用を模索する不動産会社と学んだ建築技術を実地で生かせる場を探していた有明工業高等専門学校とを繋ぎ、空き家を再生して活用する仕組みを提案。
社長から「人手不足という我々の課題を“自分ごと”として考えてくれてありがとう」と言われたことが、心から嬉しかった。


現場で学んだのは、机上の知識よりも“人との信頼づくり”の重要性。雑談を交え、相手の思いを汲み取る姿勢こそ課題解決の第一歩になる。
ベンチャー起業論で培った“調整力”は、1年間の活動の成果を発表するビジネスプランコンテストの企画でも生かされた。
コンテストは企業関係者を含め1,000人ほどが来場し、福大で一番大きな831教室のほとんどの席が埋まる。「学生には成長の場を、お客さまには快適に参加していただける環境を提供したい」という思いは同じ。でも、その方法を巡っては意見が分かれることもあった。来場する企業関係者や地域の人々、そして参加する学生の双方に満足してもらえる運営を目指し、何度も議論を重ねた。
「意見の違いを否定するのではなく、同じ目標に向かうための前向きな議論に変えていく大切さを実感しました」と振り返る。
3年次の今、ベンチャー起業論の運営執行部で学生副代表として、広報や運営、管理など複数の課に目を配る調整役、課統括を務める。
「支える立場になり、これまで“当たり前”だと思っていた環境は、誰かの支えで成り立っていたんだと気付きました」。講義の準備やコンテストの運営など、自分たちが安心して活動できる舞台の裏には、先生や執行部の努力があったと実感している。
50人のゼミ生の温度差を埋め、意欲を引き出すことが現在の課題だ。「各チームのリーダーと積極的にコミュニケーションを取って話し合うことで、思いが伝染していくのを感じています」。
“自分たち”で導き出した、“自分たち”が最善だと思う方法で目指すところに辿り着く。
視線の先には、学内の枠を越え、九州の、ひいては全国の学生たちがビジネスに挑戦できる場を創造する未来がある。

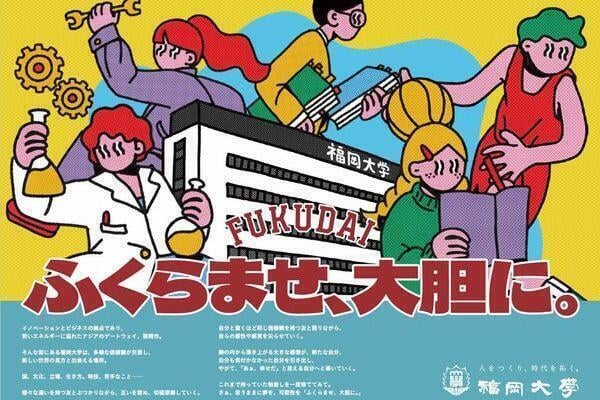
【関連リンク】
・公式Instagram(「ふくらませ、大胆に。」別企画掲載)
・経済学部ウェブサイト



















