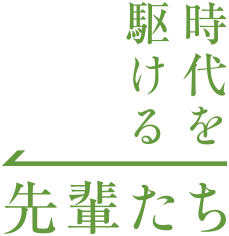
人とのつながり、信頼関係で
成り立つ仕事に、誇りとやりがいを感じる
売上高トップの焼酎メーカーで中国・四国エリアの営業を担当
居酒屋やスーパーやコンビニの酒類置場で目にする「黒霧島」「白霧島」のボトル。「くろきり」「しろきり」の愛称を、耳にしたことのある人も多いのではないでしょうか。
特に九州で深いなじみのあるこれらの焼酎を製造・販売しているのが、宮崎県都城市に本社を置く、霧島酒造株式会社。
2012年から4年連続で焼酎の売上高全国トップを誇る、日本を代表する焼酎メーカーの一つです。
南九州の風味豊かなさつまいも、都城にしかない貴重な天然水、研究し尽くされたオリジナルの麹を使った丁寧な味わい。中でも「黒霧島」は、1998年の発売以降、「芋独特の風味が少なく、甘みがある焼酎」として人気を集めるロングセラーです。
主力の芋焼酎の他にも、むぎ焼酎やそば焼酎、米焼酎、ビールなど、商品の銘柄は20種類を超えます。
その霧島酒造で、中国・四国エリアの営業を担当するのが、福岡大学出身の真方雄大さんです。
柔らかな笑顔が印象的な真方さんは入社4年目。2年前から広島を拠点に四国4県と広島県の一部を一人で担当し、毎日のように各地を飛び回っています。
地元宮崎の湧き水(霧島裂罅水)、生産農家が大切に育てた芋(黄金千貫)、それらの滋味と思いが詰まった商品を消費者に届けるのが、営業の仕事です。「酒屋さん、飲食店さん、芋の生産者さん、工場の製造スタッフ、自分たち営業マンと多くの人が関わり、お客さまのもとに商品が届いていることを、入社して改めて知りました」と話す真方さん。
積極的に人と関わり、進路のきっかけをつかむ
高校生の頃から、経済や株式など商売に関して幅広く関心があったという真方さんは、地元の本学商学部に進学しました。
授業の中で印象に残っているのが、3年次後期から専攻したゼミです。担当の藤本三喜男先生による応用経済学の解説はとても分かりやすく、興味を掻き立てられたそうです。ゼミには中国人留学生も2人在籍しており、真方さんは積極的に声を掛けていきました。「彼らは株式や市場(マーケット)などに関してとても詳しく、優秀でした。ゼミで分からないところは、よく教えてもらっていました」。
もともと人とコミュニケーションを取ることに抵抗のない性格。小学校から高校まで野球を続け、大学でも社会人が所属する地域の野球チームに2つ所属し、広く人脈を築いていきました。そして、そこでの出会いが、その後の進路を決めるきっかけになります。
「野球のメンバーの一人が酒屋さんの経営者で、練習の合間にお酒に関するいろいろな話を伺いました。飲み会などを通してお酒が身近になってはいましたが、醸造酒と蒸留酒の違いや種類などを聞くことで、お酒に関する知識の幅がぐっと広がりました」。
最も興味を持ったのが、酒屋と飲食店の関係でした。
「飲食店の多くが夜に営業するため、酒屋さんは基本的に開店前の昼に配達を済ませます。その際、飲食店の店主は自分の不在中に配達に来てもいいように、その方にお店の鍵を渡してしまうところもあるというのです。一人で30〜40軒の鍵を持っていると聞き、それほど信頼されているのかと驚きました」。
信頼関係で成り立つ仕事への憧れを持ちながら、迎えた就職活動。就職先を検討する中で、野球チームのメンバーの知り合いに霧島酒造の社員の方がいると聞き、「話を聞かせてほしい」と頼み込みました。いろいろな話を聞く中で、心を決めます。
「霧島酒造という会社は、酒屋さんだけでなく、消費者や飲食店などと密に接することを大切にしていると感じました。人とのつながりを重視する会社の姿勢に魅力を感じ、入社を決めました」。
HISTORY 先輩の足跡
1990福岡県生まれ
2010福岡大学入学
2013商学部商学科で
藤本三喜男先生のゼミで学ぶ
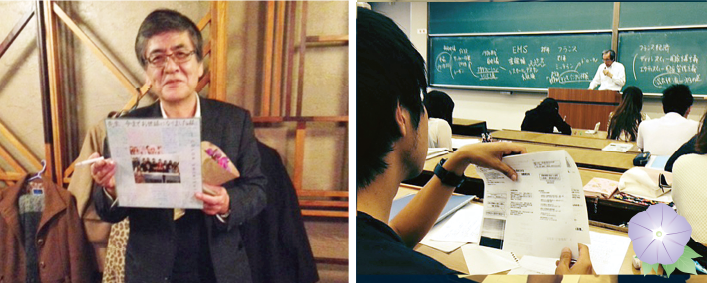
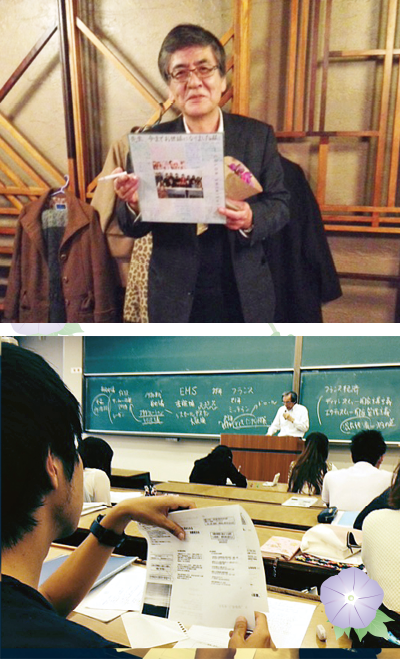
3年次後期からのゼミでは、株式や投資についての講義やディスカッションを通して、幅広く商業の知識を深めました。ゼミのメンバーは10人と少人数で分からないことは気軽に質問できる雰囲気。真方さんも疑問に感じた部分があれば積極的に研究室を訪ねたそうです。
2014福岡大学卒業

現在霧島酒造株式会社
営業職

現在は、霧島酒造株式会社 営業本部 大阪支店 中国・四国エリア担当として、日々営業活動中です。
日中に営業で回るのは平均して3件ほど。1件当たり約2時間滞在し、じっくりと話をするといいます。運転席横のコンソールには、車内での電話中にすぐにメモを取れるよう付箋を常備しています。
百年企業という
自覚を持って日々を過ごし、
挑戦を続ける。
営業先と何度も顔を合わせて信頼関係を築いていく
入社後、半年の研修期間を経て営業マンとして独り立ちした真方さんは、2年前に、大阪支店の管轄エリアである、広島拠点メンバーの一員になりました。業務の多くは外回りで、継続店を含めた各店舗への商品取り扱いの交渉です。昼は酒屋やスーパー、仕込みをしている飲食店を回り、夕方以降は開店後の飲食店を訪れます。
多くの人に親しまれているブランドなので、営業もスムーズなのでは、と聞くと、「全然そんなことはありません」と即答しました。他社の商品が取り扱われているところに、新たに置いていただくのは簡単なことではないとした上で、こう続けます。

「商品を置いてほしいと心に決めたお店は、そう簡単には諦めません。1年かけて20回ほど通いつめ、やっと置いていただいたこともあります」。
真方さんの営業マンとしてのモットーを尋ねると、
「先方が心を開いてくださったと感じるまで、一切売り込みはしません。先輩には『相手の気持ちになって考えるように』とよくアドバイスをもらいます。丁寧に時間をかけて相手のことを知りながら、逆に私たちの会社や、つくっている商品を知ってもらう。そのためには何度も顔を合わせて会話を重ねることが、何より大切と考えています」。
昨年、創業100年を迎えた霧島酒造ですが、その歴史は決して順風満帆ではありませんでした。30年ほど前はビールやウイスキー、日本酒が全盛の時代で焼酎の需要は今ほどではなく、ここ数年はワインや日本酒が人気を集めるなど、焼酎の売れ行きが伸び悩んでいます。若者のアルコール離れも深刻です。また広島や四国は日本酒の生産が盛んな地域である上、エリアによって嗜好(しこう)が少しずつ異なるため、そのような事情を把握した上で、スピーディーに提案していく必要があります。
何をどう提案するか。その答えは、やはり現場で見つけるしかありません。スーパーなどでの売り場担当者へのヒアリングはもちろん、飲食店ではお店に来られているお客さまと話しながら、情報を収集します。
「弊社の強みは、焼酎が売れない時代から今日まで、取引先さまと絶え間なく〝顔の見える関係〟をつないできたことだと思います。例えば、大阪支店の管轄エリアは、一人当たりの焼酎の消費量は少ないのですが、売り上げは伸びているのです。少しずつでもより多くの方に飲んでいただくため、私たちの商品を知ってもらう地道な努力が必要だと思っています」。
仕事の中でうれしいと感じるのはどのような時なのでしょうか。そう問い掛けたところ、
「飲食店の常連のお客さまに、私を名前や会社名で呼んでいただけた時です。また飲食店の方に〝(酒屋の)〇〇さんの紹介で霧島酒造のお酒を入れてみたよ〟と声を掛けていただくと、非常にやりがいを感じます。担当を外れた飲食店から電話をいただくことも多く、今でもつながっていることを感じ、うれしくなります」と、笑顔で話してくれました。

1916年創業の霧島酒造株式会社。本社は宮崎県都城市で、主力ブランドの本格芋焼酎「黒霧島」「白霧島」「赤霧島」のほか、多数の商品を製造販売しています。

出社後、その日の訪問する先に持参する資料などを準備して外回りへ。その後、一度オフィスに戻り事務処理を済ませ、飲食店への営業に向かいます。

1999年5月に全国発売された黒麹仕込みの本格焼酎「黒霧島」は、クセがなく飲みやすいと大ヒット。
学生時代は幅広い視野を持ち、多くの人と出会ってほしい
真方さんが、営業マンとして大事にしていることを聞きました。
「私自身の課題でもありますが、やはり気配りは大切だと思います。そして言葉選びも大事だとつくづく感じます。自分が伝えたいことと、相手の受け取り方が違うこともよくあるので、本当に難しいです」。
それでも大学時代に、留学生も在籍したゼミや地域の野球チームなどで、さまざまな立場の人たちと話してきた経験が生きていると感じています。「コミュニケーションも礼儀も社会人としての心構えも、大学時代に出会った多くの人たちと接する中で学びました」。
学生時代に、もっと視野を広げてみたかったと言う真方さんに、在学生へメッセージをいただきました。
「学生の頃はたくさんの時間があります。やりたいと思ったことは失敗を恐れずにどんどん挑戦してほしいですね。福大には各分野で活躍されているOB・OGの方も多いですし、社会人とのネットワークを広げるには絶好の環境だと思います」。
今後の抱負を聞くと、「この業界のことに限らず、幅広い分野のことを知っていきたいです。話題が広がれば、お客さまと一層深く話ができますから」と答えてくれました。
営業に求められることは自社の商品を買っていただくこと。そのためにはお客さまとの信頼関係が何よりも大切だと語る真方さん。柔らかな物腰の中にも熱意を秘め、挑戦はこれからも続きます。
この日訪れたのは、広島に来てすぐ担当を任された個人経営の酒屋さん。営業マンとして真方さんはどうですか?と聞くと「いつもニコニコしていて接しやすく、それでいてしっかり者。信頼しています」と笑顔で応えてくださいました。


