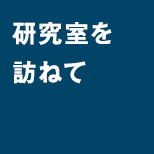
運動と健康の関係性を解明し、
「スロージョギング」を提唱
軽い運動の継続と健康増進の関係性を
50年かけて証明
田中先生は、話をしながらでも取り組める「ニコニコペース」での運動による健康増進を提唱しています。中でも、高齢者も無理なく続けられ、ウォーキングに比べてエネルギーを2倍消費する「スロージョギング」は、肥満・高血糖・高血圧など心臓血管系の罹患(りかん)リスクを抑制する運動療法として、注目されています。
自身も学生時代は、箱根駅伝の出場を目指した陸上選手でしたが、先天性の心臓病で激しい運動は無理だと宣告され、失意の日々を送ります。しかし、ドイツの医学者であるファンアーケン氏が「心拍数130/分程度で長い時間走ると心肺機能を高める」と語っていることを知り、軽運動・長時間運動に関心を持ったのが、この分野に進むきっかけとなりました。卒業後、福岡大学で運動生理の先進的な研究をしていた進藤宗洋先生(福岡大学名誉教授)の下で、本格的な研究を始めました。
進藤先生は、体が酸素を取り込む最大値であり心肺機能の高さを表す「最大酸素摂取量」の研究をしていました。ファンアーケン氏が言うように「心拍数130/分」に相当する「最大酸素摂取量の50%での運動」を続けると、本当にその最大値は上がるのか、進藤先生と共に実験を繰り返しました。
その仮説を実験で証明できたのが1970年代後半。研究を続けるうちに、最大酸素摂取量50%による軽強度・長時間の運動療法が心臓血管系の疾患の抑制や予防に効果があることも分かってきました。国際高血圧学会の会長を務めた荒川規矩男氏(福岡大学名誉教授)など、その分野での第一人者といわれる医学者と、そのメカニズムや根拠について研究を続け、エビデンス(科学的根拠)を重ねて説明してきた結果、1990年から2000年代にかけて国際的にも認められるようになりました。
昨今、その増加が社会問題になっているうつ病や認知症の予防にも、この運動療法が効果的で、そのメカニズム解明が今後のテーマだという田中先生。50年にわたる研究の集大成として、その取り組みに期待が寄せられます。
研究への思いとオフの顔を知る
3つの質問

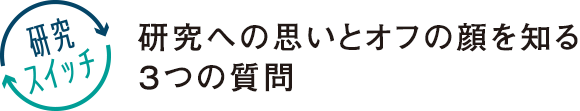
研究テーマについて教えてください。

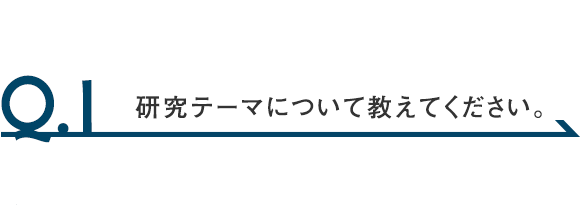
健康増進や運動能力向上につながる
運動処方の研究をしています。

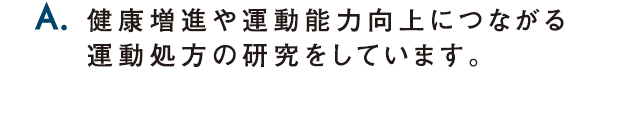
これまでの研究で、「最大酸素摂取量50%」の状態を維持する運動が、心肺機能を高めることが分かりました。また、血液量を適正化して高血圧を防ぎ、動脈硬化を抑制する善玉コレステロールの増加をもたらすこと、糖尿病の治療に有効なことをもたらすことも明らかになっています。また、内臓脂肪型肥満、高血糖、高血圧、脂質異常症などが集積した「メタボリックシンドローム」改善の最も有効な方法であることを証明しています。

学外での活動などを教えてください。

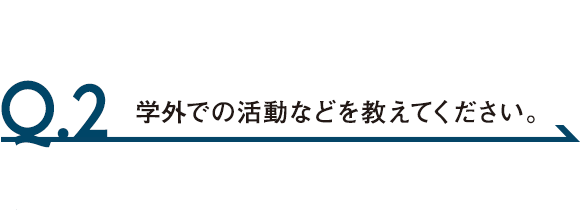
「ニコニコペース」による
「スロージョギング」の啓蒙活動をしています。

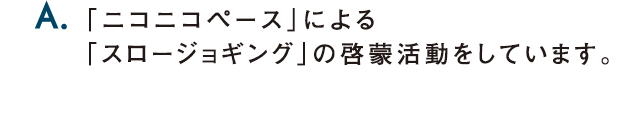
「スロージョギング」は生活習慣病の予防や健康増進につながるものとして、2009年にNHKの情報番組「ためしてガッテン」で紹介され、一気に広まりました。「スロージョギング」に関する本を日本のみならずアメリカ、韓国、ポーランド、台湾で出版したこともあって、学会はもとより講演会やイベントに招かれることが増えており、週末を中心に国内外を飛び回っています。
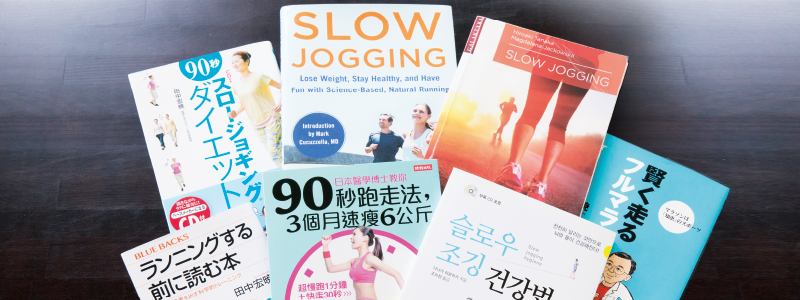
先生の趣味は何ですか?

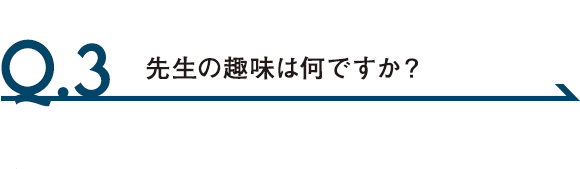
研究の成果を自ら実践し、フルマラソンに挑戦。

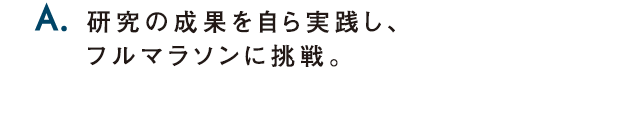
37歳の時にフルマラソンを完走しましたが、想像以上に過酷でした。ところが46歳の時、自分のニコニコペースを算出し、そのペースで完走すると3時間30分から50分で走ることができるという結果が出ました。そのころは週末に少し走る程度で、かなり太っていましたから半信半疑でしたが、実際3時間30分で完走できたんです。それからマラソンが面白くなり、今でも国内外でフルマラソンを走っています。自己ベストは50歳の時に出した2時間38分48秒です。



