
「暮らしやすいまち 」の実現へ
都市・交通計画 を研究
研究の成果は天神再開発などに反映
大学時代に都市計画の研究室に入り、実社会で生かせる研究の楽しさを感じて以来、都市計画やまちづくりの研究を続ける辰巳先生。今では福岡市天神地区の「We Love天神協議会」をはじめ自治体の都市計画や交通計画などの委員を務め、暮らしやすいまちづくりを目指した活動に幅広く携わっています。
先生が考える暮らしやすいまちとは、経済・産業が発展して活気がある中でも住民の交通手段が確保され、渋滞や事故の少ないまちのことです。まちが発展すれば渋滞が発生し、衰退すれば公共交通の減便につながるなど、都市計画と交通計画は密接な関係にあります。そのため「都市交通システム」は先生の研究の大きなテーマになっています。
現在、関わっているプロジェクトの一つが福岡市中心部の開発事業「天神ビッグバン」。老朽化したビルの建て替え、旧大名小学校跡地の活用、博多港ウォーターフロント地区の開発などを含めた大規模な都市計画です。その中で先生が取り組んだのが、天神地区・博多地区・ウォーターフロント地区を結ぶ都心循環BRT(Bus Rapid Transit)。2台の車両をつなげた大型バスは一般の路線バスよりも地下鉄に近い大量輸送性、速達性、定時性を有し、新たな移動手段として注目されています。ただ、速達性に欠かせない専用レーンの導入は実現に至っておらず、「まだ道半ば」の状態だといいます。
まちが抱える課題には、フィールドワークをもとにあらゆる角度から検討して解決策を探ります。ただ、賛否両論はつきもので、国や行政、関係者などと話し合いを続け、多くの人にとって最適な道を探っていきます。都市計画法や道路交通法など法律の知識はもちろん、関係機関の間に入っての調整力、粘り強い交渉力なども欠かせません。課題をクリアし、思い描いたまちができあがっていくのが最大の喜びです。
研究室で都市計画の基礎をはじめ、自身の経験を踏まえたまちづくりの在り方を説く辰巳先生。「公務員やコンサルタントになった卒業生と会合で顔を合わせ、頑張っている姿を見ると、嬉しいですね」と笑みを浮かべます。
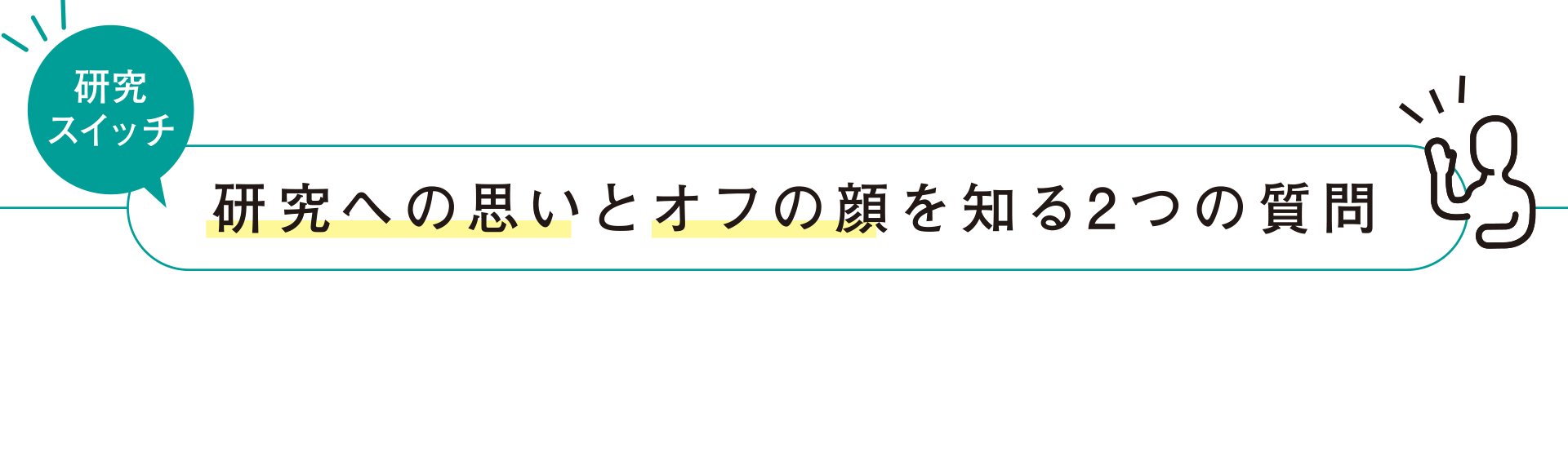
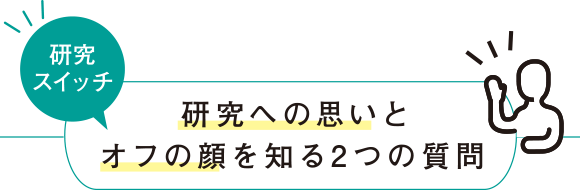
研究室では学生と
どのような研究をしていますか。
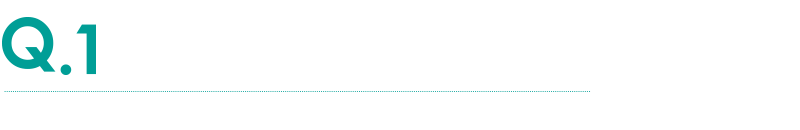
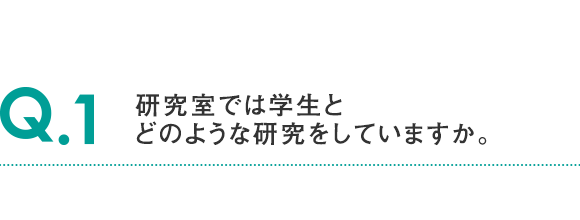
都市計画の基礎を学び、DS(ドライビングシュミレーター)を用いた
交通実験なども行っています。

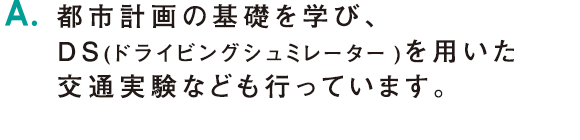
例えば「車道走行する自転車が自動車に及ぼす影響」に関する研究。自転車は従来、歩道走行が認められていましたが、現在は車道走行が原則です。そこで実際に自転車が車道を走行した場合、運転者にどのような影響があるのか、実験します。自転車の逆走などの違法行為もシミュレーターを使えば検証可能です。「歩行者道路のカラー塗装の劣化が与える影響」も画面上で色を変化させながら研究しています。

学会発表で訪れた宮崎で研究室の学生たちと
先生の趣味は何ですか?

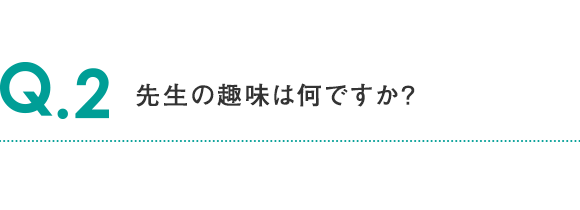
若い頃から続けている「登山」です。
頂に立った時の達成感・爽快感が大きな魅力です。

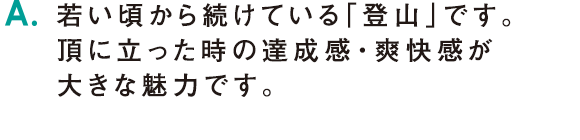
子どもの頃、親に連れられて山に行ったのをきっかけに、若い頃は仲間と南アルプスの北岳や北アルプスにも登りました。最近は腰を痛めてしまったため、家族と近郊の低山に登っています。登り始めた時は「やめておけばよかった」と思いますが、頂上に着くと達成感と爽快感が湧き、山を下りたら次の行先を考えています。その繰り返しで今も続いています。

家族と一緒によく登る宝満山にて


