現在、佐賀県鳥栖市・基山町、福岡県久留米市・小郡市の4つの地域の史跡を紹介し、探訪ルートをパソコンやスマートフォン等で検索できる「筑後川流域クロスロード歴史スポット散策システム」が公開中です。これは、福岡大学大学院工学研究科電子情報工学専攻2年次生の学生6人が、PBL(Project based Learning)の授業で取り組んだもので、管理運営も行っています。
プロジェクトは2016年から始まり、今年ウェブサイトが公開されました(11月末まで公開予定)。
携わった学生6人に話を聞きました。
●〇プロジェクトメンバー〇●
- 井口 一騎さん:リーダー、各種とりまとめ
- 高橋 司さん:議事録・マニュアル作成、デザイン、システムテスト等を担当
- 西 拓実さん:会議の進行、ページレイアウト作成等を担当
- 林田 裕一さん:開発担当
- 横山 卓哉さん:システム機能やページデザイン案の作成等を担当
-
吉井 僚佑さん:開発担当
※50音順
※以下、敬称略
- プロジェクトの内容を時系列で教えてください。
<井口>
2016年から先輩方が行っていたプロジェクトを引き継ぎ、2019年4月からこのメンバーでプロジェクトを開始しました。元々全員が福岡大学工学部出身の同級生ですが、顔を知っている程度でしたので、チームビルディングから始めました。
2019年6月には自治体の方と打ち合わせを行い、方針を決めました。2016年から続いているプロジェクトですが、担当の方が変更になったり、先輩たちから引き継いだりしましたので、自治体の方の要望に対応することが、コミュニケーションや技術の面で大変でした。
10月から12月末にかけてプログラムを作成し、その後テストや修正を繰り返し、2020年3月にサイトを公開することができました。
―今回、どのようなシステムを開発したのか、教えてください。
<高橋>
2つのシステムを作成しました。
① 利用者システム
実際にユーザーがウェブサイト上で見るものです。「おすすめルート」や「スポット」など、ページのデザインや地図の挿入、ボタンや文字の大きさの調整等、ユーザーに使いやすいものになるよう、自治体の方の要望を聞きながら、工夫を重ねました。
② 管理者編集(登録)システム
ウェブサイトで公開する内容を、自治体の方が入力するシステムです。サイトの中身を作るシステムですので、①よりも先に納品する必要がありました。
特に①について、全ての端末やブラウザで動作するように、開発やテストを行う必要がありました。それには時間と手間がかかり、とても大変でした。
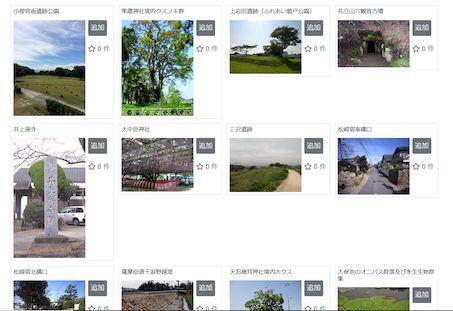
歴史スポット一覧の開発画面

マイルート編集の開発画面
